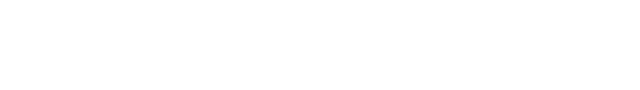認知症の方への対応方法・良い接し方のポイントは?
「認知症の人に絶対やってはいけない対応とは?」
「認知症の方への接し方や話し方のポイントは?」
「家族がもつべき心構えが知りたい」
日本では、高齢化とともに認知症の患者数も増加しています。
厚生労働省が実施した65歳以上の高齢者を対象にした令和4年度(2022年度)の調査の推計では、認知症の人の割合は約12%、認知症の前段階と考えられている軽度認知障害(MCI)の人の割合は約16%とされ、両方を合わせると、3人に1人が認知機能にかかわる症状があることになります。
参照:厚生労働省「知っておきたい認知症の基本 | 政府広報オンライン」
参照:厚生労働省「認知症および軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計」
本記事では、認知症の方への対応に関する冒頭の疑問について、詳しく解説していきます。
身近に高齢者の方がいる方や、認知症について知っておきたいという方は、ぜひご参考ください。
目次
1.接し方のポイント1-1.ポイント①否定しない
1-2.ポイント②褒める
1-3.ポイント③ストレスを与えない
1-4.ポイント④かけがえのない存在であることを認識してもらう
2.認知症の方への話し方
2-1.耳元で大きく、ゆっくり話す
2-2.目線を合わせて目を見て話す
3.家族が認知症を受け入れるまでの心理ステップ
3-1.戸惑い・否定
3-2.混乱・怒り・拒絶
3-3.あきらめ・割り切り
3-4.受容
4.家族がもつべき心構え
4-1.焦らない
4-2.認知症の人の感じ方を理解する姿勢を持つ
5.認知症の人に絶対やってはいけない7つの対応
5-1.叱る
5-2.命令する
5-3.強制する
5-4.子ども扱いする
5-5.行動を制限する
5-6.役割を取り上げる
5-7.何もさせない
6.認知症の方とは適切な対応を学んで受容しながら接しよう
接し方のポイント
まずは早速、接し方のポイントから解説していきます。
主なポイントは以下の4つです。
- 否定しない
- 褒める
- ストレスを与えない
- かけがえのない存在であることを認識してもらう
それぞれ見ていきましょう。
ポイント①否定しない
認知症の方と接する際に「否定しない」ことは基本中の基本です。
認知症の方が現実と異なる事を話しても、彼らの記憶や感覚を否定するのではなく、理解しようとする姿勢が大切です。
記憶や認知のズレからくる彼らの話には、直接的な訂正や否定はしない方が良いでしょう。
それは彼らに不必要なストレスや混乱を与えてしまい、コミュニケーションの妨げになります。
彼らの発言に対しては、共感を示し、安心感を伝えることで、ポジティブな交流を保てます。
正しい情報を伝えたい衝動を抑え、彼らが感じていることにフォーカスしましょう。
それが穏やかな関係を築くことにつながります。
ポイント②褒める
認知症の方への接し方で「褒める」というポイントは、とても重要です。
認知症の方が日常生活で何か小さなことを成し遂げたとき、たとえそれがごく簡単なことであったとしても、積極的に褒めることで自尊心をサポートし、モチベーションの向上につなげましょう。
彼らがかつてできたことが困難になっている今、成功体験は非常に価値があります。
小さな成功を称賛することで、彼らは愛され、評価されていると感じ、これがさらなるポジティブな行動を引き出す可能性があるのです。
常に優しさと尊厳を持って接しながら、彼らのできたこと、頑張っていることを見つけ、褒めるよう心掛けましょう。
ポイント③ストレスを与えない
認知症の方とのコミュニケーションにおいて「ストレスを与えない」ことが大切です。
ストレスは認知症の症状を悪化させる原因のひとつであるため、彼らの感情や能力を尊重し、忍耐強く接することが重要になります。
また、複雑すぎる選択や急いで行動を促すなど、プレッシャーを感じさせる状況は避けましょう。
周囲の環境が安定していて予測可能なものであれば、人は安心して過ごすことができるものです。
日常生活に一定のルーチンを提供することも、ストレスを減らすのに寄与します。
安心して過ごせる環境作りを心がけることで、彼らの穏やかな気持ちを保つ手助けとなります。
ポイント④かけがえのない存在であることを認識してもらう
認知症のご家族と向き合う毎日は、戸惑いや不安に包まれることも少なくありません。
それでも、ご本人が「自分はここにいていい」と感じられることは、心の安定や尊厳を守るうえで欠かせない支えとなります。
「あなたは大切な存在です」という思いは、特別な言葉や特別な出来事を通さなくても、日々のさりげない関わりの中で十分に伝えることができます。
日々のささやかなやり取りこそが、その思いを伝える手段になります。
たとえば、目を見て話を聴く、うなずきながら耳を傾ける、できたことに気づいて「ありがとう」「うれしいね」と声をかけることもおすすめです。ご本人の心に家族の言葉があたたかく届き、自尊心や自己肯定感を支える力になります。
認知症の方は、ときに感情が不安定になったり、理由のはっきりしない不安を抱えたりすることがあります。
だからこそ、「あなたがいてくれて嬉しい」「一緒に過ごせてありがたい」といった思いを、日々の言葉やふるまいを通じて、丁寧に伝えることが大切です。
そのような働きかけの積み重ねが、ご本人に安心感をもたらし、「自分は大切にされている」と実感してもらうための確かな支えとなります。
認知症の方への話し方
次に、認知症の方への話し方を見ていきましょう。
ここでは最重要となる以下の2つを解説します。
- 耳元で大きく、ゆっくり話す
- 目線を合わせて目を見て話す
それぞれ確認してください。
耳元で大きく、ゆっくり話す
認知症の方とコミュニケーションをとる際には、ゆっくり、はっきり、穏やかに話すことが大切です。
大きな声で急に耳元から話しかけると、かえって驚かせてしまうこともあるため、相手の様子を見ながら落ち着いた声のトーンで話すことが推奨されています。
認知症を患うと、聴力だけでなく、言葉の意味を理解したり内容を整理したりする「情報処理能力」も低下することがあります。
そのため、短く、具体的で、わかりやすい表現を使うことが効果的です。
声をかけるときには、まずご本人の名前を呼んで注意を引き、目を合わせてから話し始めましょう。
話す内容は一度にたくさん詰め込まず、一文ずつ、区切りながら伝えるようにすると、理解しやすくなります。
また、早口やまわりくどい言い回しは避けましょう。聞き返しがあっても焦らず、同じ調子で繰り返して伝えることが大切です。
目線を合わせて目を見て話す
認知症の方とコミュニケーションを取る際には、目線を合わせ、やさしく目を見ることがとても効果的です。
視線を交わすことで、相手に対する関心や敬意が伝わり、「自分は大切にされている」という安心感をもってもらいやすくなります。
また、言葉だけでは伝えきれない感情や意図を、目元の表情や視線の動きから読み取ることができます。
これは、認知症の方とのコミュニケーションにおいて非常に重要な手がかりです。
ただし、じっと見つめすぎると威圧的に感じられることがあるため、自然で優しいアイコンタクトを心がけましょう。
相手が話しやすい距離と視線のやり取りを意識することで、無言のうちにも共感とやさしさが伝わります。
このような目線の配慮は、認知症の方との信頼関係を築く上で、かけがえのない一歩となります。
家族が認知症を受け入れるまでの心理ステップ
認知症の診断を受けたとき、家族は深い戸惑いや不安を感じます。
それを乗り越え、現実を受け入れていくまでには、いくつかの心理的な段階を経るといわれています。
ここでは、認知症の家族を持つ方がたどるとされる4つの心理ステップをご紹介します。
- 戸惑い・否定
- 混乱・怒り・拒絶
- あきらめ・割り切り
- 受容
それぞれ順に解説していきます。
戸惑い・否定
認知症の診断を受けたとき、多くの家族が最初に経験するのが「戸惑い」や「否定」の気持ちです。
それまでしっかりしていた家族が、急に言動に違和感を見せたり、できていたことができなくなったりすると、何が起きているのか分からず、大きな不安と混乱に包まれます。
「認知症だなんて信じられない」「医師の診断が間違っているのではないか」と感じることも珍しくありません。
このような反応は、愛する人の変化に直面したときに生じる自然な心の防衛反応であり、認知症に限らず、さまざまな病気や困難を前にしたときにも見られます。
この時期の家族は、他人に相談することさえためらい、悩みをひとりで抱え込んでしまう傾向があります。
特に、尊敬していた親や信頼していた配偶者が対象の場合、その現実を受け入れるには、どうしても時間が必要になります。
それでも、日々の生活の中で症状の変化や影響が少しずつ明らかになってくると、現実に向き合う準備が整いはじめます。
混乱・怒り・拒絶
認知症の診断を受けた家族が、「戸惑い・否定」の段階を経て直面するのが、「混乱・怒り・拒絶」のステップです。
日々の暮らしの中で、ご本人の症状や変化がはっきりと現れてくると、家族は強い混乱に陥ることがあります。
理解しようとしても、状況の複雑さや先の見えない不安に圧倒され、精神的に追い込まれてしまうこともあります。
その結果、怒りや苛立ちといった感情が湧き上がり、「なぜ自分の家族が」「どうしてこうなったのか」と、運命や周囲に対して強い思いを抱くことがあります。
このような中で、医療や介護の体制に対する不信感が芽生えたり、ご本人の言動を受け入れられず、心の中で拒絶するような気持ちが生まれることもあるでしょう。
「もう限界かもしれない」と感じることがあっても、それは決しておかしなことではありません。こうした感情は、誰もが通る可能性のある、ごく自然な反応です。
この時期は、家族にとって最も感情的な負荷がかかる段階だと言われています。
だからこそ、話を聞いてくれる人の存在や、専門職とのつながり、同じ立場の人との交流が、大きな支えになります。
あきらめ・割り切り
認知症の診断を受け入れる心理的プロセスの中で、「あきらめ・割り切り」の段階に至ると、家族は次第に、病気は避けられず、状況を変えることはできないという現実を認識するようになります。
この頃には、初期の否定や怒りの感情が落ち着きはじめ、病気とどのように共に暮らしていくかを考える心の余裕が生まれてきます。
まだ完全に受け入れられたわけではないかもしれませんが、現実を冷静に見つめ、「これがこれからの日常なのだ」と受け止める準備が少しずつ整っていきます。
この段階では、介護に必要な情報を集めたり、支援制度や医療・福祉サービスを検討したりするなど、実際の行動や具体的な準備に踏み出すことが多くなります。
家族は少しずつ、「できることを、できる範囲で」取り組もうとする姿勢に変化していきます。
受容
家族が認知症という現実を受け入れる「受容」の段階に達すると、少しずつ病気に対する理解が深まり、心にも落ち着きが生まれてきます。
戸惑い、怒り、そしてあきらめの過程を経て、ようやく今の状況を穏やかに受け止める準備が整い、これからの暮らしの中で何を大切にしていくかを考えられるようになります。
この段階では、認知症のご本人に対する見方も変わってきます。
「病気と向き合う」ではなく、「ともに生きる」ことへと、家族の意識が自然と移行していきます。
その根底には、深い共感と変わらぬ愛情があります。
現実を受け止めた家族は、より良いケアの方法や支援制度、同じ立場の人たちとの交流など、前向きな情報を求めるようになります。
日々の暮らしの中で、ご本人とともに喜びを見つけていくことが、次の目標になっていきます。
関連記事:認知症の初期症状と早期発見のポイント
赤羽すずらんメンタルクリニックでは、必要に応じて医師や専門スタッフがご家族のお気持ちにも丁寧に寄り添い、今後の対応について一緒に考える時間を大切にしています。
外来受診が難しい方には、訪問診療によるご相談も承っております。「どうしてよいかわからない」とお感じのときは、お一人で抱え込まず、ぜひ一度ご相談ください。
家族がもつべき心構え
いざ家族が認知症になったとき、不安に思う方が多いでしょう。
そこでここからは、家族がもつべき心構えを2つ紹介します。
心構えといっても、難しいことではありません。
- 焦らない
- 認知症の人の感じ方を理解する姿勢を持つ
まずは落ち着いて、そして優しく受け止めましょう。
それぞれのポイントをさらに深掘りしていきます。
焦らない
認知症の家族が心がけるべき「焦らない」という心構えは、病気との付き合い方を学ぶ際に非常に大切です。
認知症の進行は人それぞれであり、日々変化する状況に素早く対応する必要があるため、焦りは感じやすいですが、これは患者さんにも伝わりやすく、不安や混乱を引き起こす原因にもなります。
ゆっくりと状況を受け止め、一つひとつの変化に対応することで、本人も家族もより良いケアを行う土台を作れます。
焦らず、一緒に過ごす時間を大切にしながら、できる限りのサポートを提供する姿勢が推奨されます。
こちらの記事では、認知症が進行する原因についてくわしく解説しています。あわせてぜひご覧ください。
認知症の人の感じ方を理解する姿勢を持つ
認知症の方の感じ方を理解しようとすることは、ご家族にとってとても大切な心構えのひとつです。
認知症になると、目の前の状況を理解したり、自分の気持ちをうまく伝えたりすることが難しくなることがあります。
そのようなときこそ、ご家族がご本人の立場になって考え、気持ちに寄り添おうとする姿勢が、安心感や信頼関係につながります。
また、日々の小さな表情やしぐさの変化に気づくことで、ご本人が何を感じているのか、どんな支援を必要としているのかに、より深く気づけるようになります。
このような共感を大切にしたかかわりは、ご本人の不安やストレスを和らげるだけでなく、ご家族全体の絆を深め、より穏やかな関係を築く大きな力になります。
認知症の人に絶対やってはいけない7つの対応
最後に、認知症の人に絶対やってはいけない7つの対応を紹介して終わります。
- 叱る
- 命令する
- 強制する
- 子ども扱いする
- 行動を制限する
- 役割を取り上げる
- 何もさせない
多くは基本的なことですが、中には「何も差せない」など、つい善意でやってしまうことも含まれます。
それぞれ、理由とともに確認してください。
叱る
認知症の方に向けて頭ごなしに叱る行為は、絶対に避けるべきです。
認知症の進行は、その人の意志とは無関係に記憶や判断力が低下していくため、日常生活での困りごとや誤った行動は避けがたいものです。
叱責は彼らの自尊心を傷つけ、不安やストレスを増大させることにつながりかねません。
また、攻撃的な反応を引き出す原因ともなり得ます。状況の説明や落ち着いて対処する方法を優しく教え、支持する姿勢が重要です。
認知症の方は感情の影響を強く受けるので、常に尊重と理解をもって接することが不可欠といえます。
命令する
認知症の方に命令形式で物を言うのは避けましょう。
命令はしばしば圧力を与え、彼らを防御的にさせることがあります。
認知症には自立を促す温かい支援が必要です。
命令ではなく、選択肢を提供し、決定に参加できるよう支えることで、彼らの自尊心や自律性を尊重しましょう。
穏やかな口調と肯定的な言葉選びで、安心できるサポートを提供することが鍵です。
強制する
認知症の方に対して「強制する」ことは、信頼関係を損ね、ストレスや抵抗感を引き起こすため、避けるべき対応です。
認知症は症状が日々変動し、その人なりの世界観を持っているため、自分の意思や感覚を尊重しない行為は彼らを混乱させ、不安や反発を生じさせる可能性があります。
日常生活においても、安心して選択できる環境を整え、必要であればゆっくりと選択肢を提示し、彼らのペースで動けるよう支援することが重要です。
常に患者さんの尊厳を心に留め、優しく、根気よく接するようにしましょう。
子ども扱いする
認知症の方を子ども扱いすることは、彼らの尊厳を損ない、自尊心を傷つける行為です。
大人としての経験や自己のアイデンティティを持つ彼らに対し、話し方や対応が幼稚化してしまうと、それは人格を否定することにもつながりかねません。
また、依存を増やす原因にもなり、彼らが持つできるだけの能力を発揮する機会を奪ってしまいます。
だからこそ、常に認知症の方を大人として尊重し、対等なコミュニケーションを心掛けましょう。
行動を制限する
認知症の方の自由を不当に制限することは、彼らの生活の質を大きく下げる可能性があります。
自己決定の権利と自由という基本的人権を侵害する行為であるからです。
たとえば、安全は確保しながらも、できるだけ通常の生活活動や社会参加を続けられるよう配慮が必要です。
不必要な制限は彼らのストレスを増加させ、社会的孤立や不安、抑うつを引き起こしがちです。
そこで大切なのは、継続的なコミュニケーションと個々の状況に合わせた適応策をとること。
安全と自立のバランスを見極めながら、できるだけ普段どおりの日々を送れるよう支援しましょう。
役割を取り上げる
認知症の方の役割を取り上げることは、彼らの自尊心とアイデンティティを損なう行為です。
たとえば、日常生活のタスクを自発的に行えなくなった場合でも、能力に応じた小さな任務を彼らに委ねることが重要です。
これにより、彼らは有意義で必要とされているという感覚を保ち、自信と自己効力感を維持できます。
そのため、できる限りの自立を促し、支援が必要な時には優しく助けを提供しましょう。
常に彼らの尊厳を守り、人間としての価値を認める態度が大切です。
何もさせない
認知症の人に「何もさせない」という対応は、その方の自尊心や自立心を損ない、症状を悪化させる可能性があります。
彼らが独自の意志や能力を発揮することは、自己価値感の向上につながり、認知機能の維持にも役立ちます。
日常生活の小さなタスクであっても、できる限り本人に参加してもらい、サポートを提供することが重要です。
完璧でなくても良いので、認知症の方が自分の能力に応じた活動を行うことを奨励しましょう。
これにより、彼らの生活に意味と目的をもたらし、より充実した日々を送ることにつながります。
無理なく彼らを支援し、できることを尊重する姿勢が大切です。
認知症の方とは適切な対応を学んで受容しながら接しよう
認知症の方への適切な対応には、理解と受容が不可欠です。
調和のとれた関係を築くためには、その人の過去やパーソナリティを尊重し、彼らの現在の状況を認めることが重要です。
コミュニケーションをとる際には、ゆっくり、はっきりと話し、非言語的なサインにも注意を払いましょう。
彼らの意見や願いを尊重し、できる限り自己決定を尊重するよう努めることも重要です。
認知症の方にとって安定した日常と継続性は安心感をもたらすため、一貫性のあるケアルーチンを実践することも大切。
また、彼らが直面する挑戦は変わり続けるため、その時々の状況や能力に合わせた柔軟性も求められます。
愛情と優しさをもって接し、安心と尊厳を守ることで、認知症の方も家族もより良い生活を送ることができるでしょう。
赤羽で心療内科をお探しの方はコチラをご覧ください。
監修者