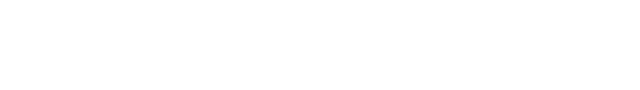睡眠障害の原因とは?不眠症状を抱える人の割合や治し方も解説
睡眠障害の原因は、大きくわけて5つに分類されます。
自分がどのタイプに当てはまるかチェックすることで、解決策が見えてくるでしょう。
この記事では、睡眠障害の原因をタイプ別に詳しく解説します。
睡眠障害の治し方や、不眠で悩んでいる方の割合などもまとめているので、ぜひ参考にしてください。
睡眠障害とは
睡眠障害とは、眠れない、寝付けないといった、睡眠に関して何かしらの問題を抱えている状態です。
不眠症だけでなく、過眠症や睡眠時のねぼけ行動なども挙げられます。それぞれの症状には異なる原因があり、適切な診断と治療が必要です。
また、睡眠障害で最も多いとされているのが不眠症状であり、日常生活に支障をきたすケースも見られます。
原因によっては、通常の睡眠薬による治療ではなく、精神科や脳神経内科医などへ相談することで改善が見込めます。
参考:厚生労働省 厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト「不眠症」
睡眠障害のおもな原因
睡眠障害のおもな原因は、おもに以下の5つに分類されます。
● 心理的原因:ストレス
● 身体的原因:外傷や関節リウマチ
● 精神医学的原因:不安症状や抑うつ
● 薬理学的原因:薬やアルコール
● 生理学的原因:生活環境の変化
自分がどのタイプに当てはまるのかチェックしてみましょう。
心理的原因:ストレス
心理的原因は、おもにストレスに起因する不眠症状です。
対人関係や仕事のプレッシャー、身近な人との死別など、何らかの強いストレスを受けている可能性があります。
この場合、眠れなくなった前後の出来事を振り返ると、原因が明らかになります。
心理的原因による睡眠障害は一時的に発症するケースが多く、数週間程度で落ち着きます。不眠症状が3ヶ月以上続いている場合は慢性不眠症の可能性が疑われ、治療が必要となるケースもあります。
身体的原因:外傷や関節リウマチ
身体的原因は、かゆみや痛みなど、不眠の原因が身体にある場合の症状です。
おもに以下のような病気や症状があげられます。
● 外傷
● 関節リウマチ
● 湿疹蕁麻疹
● 喘息発作
● 頻尿
● 花粉症
● アトピー
● むずむず症候群
これらの症状や疾患は、夜間の不快感を引き起こし、睡眠の質を低下させる可能性があります。
関節リウマチや外傷による慢性的な痛みは、就寝時にとくに影響を及ぼします。また、湿疹や蕁麻疹などの皮膚疾患はかゆみを伴い、睡眠を妨げる原因となることも。
身体疾患の原因を追究し、適切な治療を受けることが睡眠障害への対策につながるでしょう。
精神医学的原因:不安症状や抑うつ
精神医学的原因は、不安症状やうつ病といった神経症が原因で睡眠障害を起こすケースです。
おもな原因とされる症状は、以下のとおりです。
● うつ病
● 不安障害
● 神経症
● 統合失調症
● アルコール依存症
うつ病が原因で不眠症状を引き起こしているケースもあるため、憂うつ感が続いているときは、重症化する前に専門医に相談しましょう。
また、睡眠障害が慢性化している場合も抑うつ状態の可能性があります。
薬理学的原因:薬やアルコール
薬理学的原因は、服用している薬やアルコール、喫煙、カフェインなどが引き起こす不眠の症状です。
薬理学的原因は、おもに以下のとおりです。
● 服用している薬
● 飲酒(アルコール)
● 喫煙(ニコチン)
● コーヒーなど(カフェイン)
抗がん剤やステロイド薬、中枢神経に働く薬などがあります。
服用している薬が原因で睡眠障害を起こしている可能性のある場合は、かかりつけの医師に相談してみましょう。
また、飲酒や喫煙、カフェイン摂取が習慣化している方も、不眠症外の改善のために見直しが必要かもしれません。
生理学的原因:生活環境の変化
生理学的原因は、体内リズムの乱れによって睡眠障害が引き起こされるケースです。
夜更かしや勤務シフトによる睡眠時間の不規則な変動など、さまざまなケースがあげられます。
その他、周囲の騒音や寝室の室温が適切ではない場合など、就寝時の環境が影響しているケースも。
睡眠障害を抱える人の割合
厚生労働省の調べによると、日本で睡眠障害を抱える人の割合は、一般成人の30〜40%程度とされています。
不眠症は国民病とも言われ、多くの方が何らかの形で睡眠の問題を経験しています。実際に、成人の5%が不眠に関する薬を服用しているとの報告も。
また、慢性不眠症の方は約10%とされており、60歳以上になると半数以上の方に不眠症状があると認められています。
とくに女性の方が、睡眠障害を抱えている人の割合が多いことも知られています。
睡眠障害の対処法
睡眠障害は、慢性化してしまうと自然に治ることはあまり期待できません。慢性化する前に、原因に応じた対策を講じることが大切になります。
自分でできる治し方の一つに、「認知行動療法」という心理療法が存在します。
「眠れない」といった、睡眠に対する偏った認知を正し、睡眠習慣を身に付けるのが目的です。
認知行動療法に基づいた睡眠習慣を身に付ける方法は、おもに以下のとおりです。
● 眠くなるまで寝床に入らない
● 寝床は眠れる場所と認知される
● 朝は太陽の光を浴びる
● 日中は活動的に行動する
● 夜は就寝に向けてリラックスする
● 睡眠にメリハリをつける
なお、興味の喪失や、意欲、食欲の低下がみられる場合は、うつ病の可能性が疑われます。
また、気負いすぎてしまうと、ストレスで睡眠障害が慢性化してしまう恐れがあります。専門知識を有するカウンセラーに相談することで気持ちが軽くなり、心理的負担も減らせるでしょう。
参考:国立精神・神経医療研究センター「睡眠障害ガイドライン」
まとめ
睡眠障害の原因は、「心理的原因」「身体的原因」「精神医学的原因」「薬理学的原因」「生理学的原因」の5つのタイプに分類されます。
不眠症状を引き起こす原因を知ることで、適切な対策や治療をおこなうことが可能です。
睡眠障害の原因の多くは、ストレスや不安症状といった、精神的な負担によって引き起こされています。
ストレスや不安の原因を追究し、思考パターンの偏りを修正することで、睡眠の質を上げられるかもしれません。
赤羽で心療内科をお探しの方はコチラをご覧ください。
監修者