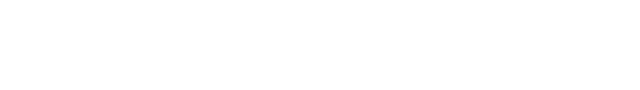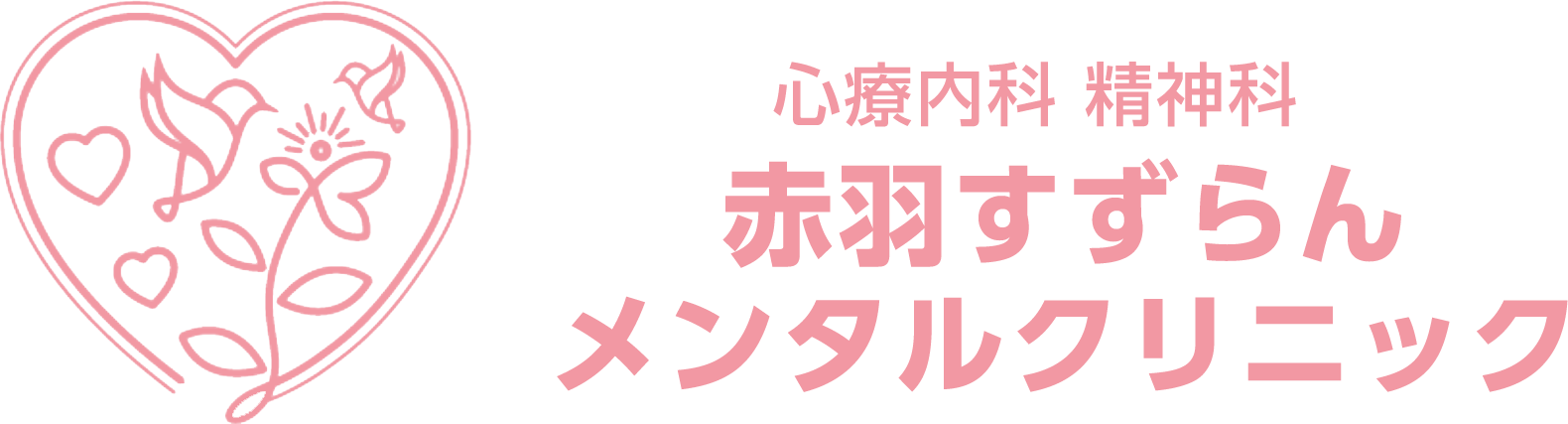ひきこもりになってしまう人の原因や脱出方法

「家族がひきこもりになってしまった」「家から出たくない、人に会いたくない」そういったきっかけで、ひきこもりの原因や脱出方法は何なのか疑問を抱く人は多く感じます。ひきこもりが甘えやサボりととらえられ、理解のされにくさから頭を抱える人もいるのではないでしょうか。
今回は、ひきこもりになる原因や脱出方法について解説します。また、本記事を読めば、ひきこもりの人と接触するには何に気を付ければいいのか、ひきこもり本人の心理を踏まえながら対処方法についても分かります。自宅にひきこもり状態の方がいる家庭や、ひきこもり気味の現状をどうにか解決したいと思う方にはとくにおすすめです。
ひきこもりになってしまう原因
ひきこもりの大きな原因は、挫折体験と言われています。ここでは、対人関係の苦手意識や生きがいをなくした喪失感、複雑な要因が絡み合って患った精神疾患など、ひきこもりになる原因3つを解説します。
【原因1】対人関係の苦手意識
ひきこもりの大きな原因は、対人関係と言われています。学生時代のいじめや職場の付き合い、失恋など、人と接することが苦手になり、誰とも会いたくない、関わりたくない思いからひきこもってしまいます。 なかでも学生時代に不登校になった経験のある人は、ひきこもりになる確率が高いと言われています。入学や就職など、環境が変わる際は大きなストレスとなり、新しい場になじめない孤独感や仕事上のコミュニケーションが上手く行かないなどで、ひきこもりに発展するきっかけです。
【原因2】仕事の失敗や後輩に先を越されたなどの自信の喪失
これまで積んできた実績に自信を持っている人ほど、挫折した時のダメージは大きいものです。とくに30代~40代の中堅的な地位の人は、後輩たちから頼られることが多く、優越感を覚える人もいます。 ただ、そんな時優秀な後輩が自分以上のスキルを持っているほか、自分の得意分野を超える技術があると、プライドの高い人はとくに自信を喪失しやすいです。大勢の前で恥ずかしい思いをしたり、仕事を失敗して叱られたなどの経験も、ひきこもりに繋がる可能性があります。
【原因3】生きがいを感じない
ひきこもりの原因は、生きがいを感じないことも原因の一つです。自分の強みや得意分野を他人にくじかれた、最愛の人を失ったなどの消失感から、家にこもって外界を遮断するようになります。 また、女性の場合は結婚や出産を機に職場を離れたときなど、環境が大きく変わった際にひきこもりになりやすいと言われています。一旦職場を離れると社会復帰しづらく、復帰したくてもできず現実に打ちのめされ、自信をなくしてひきこもる人もいます。
【原因4】精神性疾患を抱えている
うつ病やパニック障害などの精神疾患を抱える人は、自分の安全を守ろうとしてひきこもりになりやすいと言われています。精神疾患の診断を受けていなくても、以下に当てはまる方は気を付けましょう。
- 責任感が強くイラだち焦りやすい
- 傷つきやすく自信がない
- 周囲に信じられる人がいない
- 人に助けを求められない
- 外部刺激に敏感
これらの特徴は、日本人に多い気質です。特に精神疾患を抱える方は他人思いで真面目で繊細な方が多い傾向があります。ひきこもりは、自分の心を守るための防衛反応です。誰にでもなる可能性はあり、決して他人事ではありません。
こちらの記事では、うつにかかりやすい人の性格について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
真面目な人が多い?うつにかかりやすい人の性格を解説
ひきこもりから脱出するための方法
ひきこもりから脱出するためには、本人の行動力と周りのサポートが大切です。ここでは、3つのひきこもりから脱出する方法を解説します。
【方法1】散歩をしながら日光浴をする
ひきこもりから脱出するにはとりあえず家から出ることです。服を着替えて、家の周りを少しだけでも散歩してみましょう。日光や人目が気になるなら夜から始めてみるのも効果的です。慣れてきたら日中の散歩にもチャレンジしましょう。太陽を浴びると体内でビタミンDが生成されます。 また、太陽を浴びると心を安定させるセロトニンというホルモンが分泌され、精神の安定や平常心、直観力を上げるなどの効果もあります。まずは5~10分程度の外出から、少しずつ始めてみましょう。
【方法2】家族以外の人と会話をする
ひきこもりは、実家暮らしや結婚している方もなります。家族と話しているから問題ないと思わずに、家族以外の人と顔を合わせて話をしてみましょう。顔を合わせて会話をすると、失っていた自信を取り戻しやすくなり社会復帰しやすくなります。 最初は電話やアプリでのチャットなどでの会話から始めるなど、気軽な方法から試してみましょう。お店の人にあいさつやありがとうと伝えてみるのもおすすめです。声が小さく伝わらなくても、声に出すことに意味があります。徐々に慣れていくことが大切です。
【方法3】小さな目標を立てて成功体験を重ねる
ひきこもりから脱出するには、目標を少しずつ達成していくことが大切です。散歩で太陽を浴びることや、家族以外の人と会話をすることなどから始めても良いでしょう。自分で立てた目標を達成できると自信ややる気につながり、精神を安定させてくれます。 最初のうちは、「午前中に起きる」や「通話で友達と話す」など簡単な目標をつくりましょう。これらを習慣にできれば、ひきこもりから脱出できます。焦らずに少しずつ、毎日1つずつでもいいので継続することから始めてみましょう。
ひきこもり本人に対して出来る周りのサポート
ひきこもりの人に対して、周りの人はどんなふうにサポートしたらいいのでしょうか。ひきこもり本人の心理を交えながら解説します。家族や友達にひきこもりの人がいる方は必見です。
【サポート1】こまめに話しかける
ひきこもりの人は、消極的になっていることが多いので、何気ない話を持ちかけてみましょう。話しかけるのが困難な場合はチャットや手紙でも構いません。本人の負担にならない程度に、話しかけることが大切です。 ひきこもりは、本人にポジティブな出来事や声かけにより、安心感や共感、理解をすることで、本人がひきこもりから脱したいと意欲が芽生えます。本人が話しかけやすい雰囲気や環境をつくることが 解決につながります。
【サポート2】気持ちに寄り添って肯定する
ひきこもる理由は人それぞれで、複雑な心理状態の場合があります。ひきこもっていた本人が話をするときは上手く話せないかもしれませんが、焦らせずに寄り添って本人が伝えたいことは何なのかを引き出すことが大切です。 そのためには、本人を認めて肯定することが大切で、「辛かったね」「よく頑張ったね」と肯定する言葉を掛けましょう。ひきこもっている人は自信がなく心が傷ついている状態の人が多いので、意見や指摘はあまり効果的ではありません。相手がホッとするような言葉を掛けましょう。
【サポート3】無理強いはしない
家族からすると、早くひきこもっていないで社会復帰して欲しい。心配のあまりすぐに病院に連れていきたいと思うでしょう。しかし、こればかりは本人の意思が大切です。今はそっとして欲しいのか、助けが欲しいのか素直に聞いてみるといいでしょう。 良かれと思ってした行動が相手を傷つけて裏目に出ることもあるので、本人の意思による行動が大切です。無理強いをすると余計にひきこもる可能性があるので、気長に待ってみましょう。
ひきこもりから脱出するには、本人の意思と周りの支えが必要
ひきこもりから脱出するには、本人の意思はもちろん重要ですが、意思を固めるためのきっかけも大切です。きっかけは、年齢の境目や家族の結婚や退職などのターニングポイントが身近にあることです。自分は何も変わらないという焦りからひきこもりを脱しようと決意するかもしれません。 自分の力や家族のサポートだけでは難しいと感じたなら、自治体のひきこもり相談センターやメンタルクリニックで相談してみるのもおすすめです。 ひきこもりから脱出するには、本人の意思と周りの支えが必要 ひきこもりの原因や対処法、周囲の人が行えるサポート方法について解説しました。ひきこもりは、対人関係が上手くいかないことや挫折によるものがほとんどです。ひきこもりを脱出するには本人の意思と周りの友人や家族のサポートが必要です。ひきこもり当人の意思を尊重しましょう。 ただ、支える家族にも負担は大きいと思います。赤羽すずらんメンタルクリニックでは、ひきこもっている本人はもちろん、ご家族の方からの相談も受け付けております。気兼ねなくご相談ください。
赤羽で心療内科をお探しの方はコチラをご覧ください。