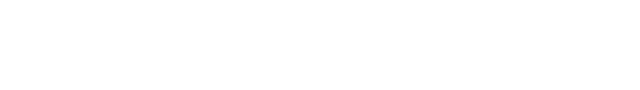中学生で不登校になる原因とは?意外なところに隠れているきっかけ
不登校児童生徒数は小学校、中学校ともに近年増加の傾向です。
文部科学省の最新の調査によると、(令和6年3月公表)では、令和4年度の不登校児童生徒数は過去最多の29万9千人となっています。
このうち中学生の不登校率は約6.0%(16.6人に1人)と高く、クラスに2~3人いる計算になります。
参考:文部科学省委託事業|不登校の要因分析に関する調査研究報告書
不登校の中学生を見守る親や周囲の人にとっては、いち早く不登校の問題を解決し、毎日登校できるようになってほしいと思いますよね。
しかし、不登校の原因にはいろいろな問題が絡み合っていることもあれば、本人にも原因が分からないこともあります。
この記事は、不登校の中学生に関わる方に向けて、文部科学省の調査などをもとに、不登校の原因についてくわしく解説しています。 不登校の原因は学校だけでなく、意外なことが引き金になっていることもがあるので、ぜひ参考にしてください。
不登校とは?
文部科学省によると、不登校とは病気や経済的な理由による欠席を除き、年度内に30日以上欠席している状態を指します。 しかし、先にもあげた文部科学省の不登校に関する調査結果によると、欠席日数30~89日の者より90日以上欠席している者の人数の割合が6割以上を占めています。
このことから、不登校の目安は30日以上となってはいますが、数値的には90日以上休む者が多く、非常に長い間不登校になっている者が多いという実態も見えてきます。
また、27人に1人が不登校という計算になるため、クラスに1~2人はいる計算に。
そうなると、近年では不登校はそんなに珍しいことではないのかもしれません。
しかし、身近に関わる大人からすると、やはり毎日学校に行ってほしいものですよね。
そこで、中学生が不登校になる原因について探っていきましょう。
中学生で不登校になる原因
中学生で不登校になる原因はさまざまです。
【原因1】学校が原因の場合
不登校の原因には、学校での人間関係やいじめ、勉強に関する悩みが挙げられています。 小学校とは環境がガラッと変わり、中学校で新しく人間関係を作っていく中で、うまく友人関係が築けなかったり、いじめがあったりしたことが原因で、不登校になる場合があります。
また、中学校では小学校よりも学習内容が高度になるので、授業についていけず、劣等感や無力感を感じて学校に足が遠のくケースもあるようです。
【原因2】家庭が原因の場合
家庭内の問題が原因で不登校になる場合もあります。
例えば、家庭の経済状況が良くなく、通学に困難が生じるとき。 もしくは、親同士の喧嘩、離婚などによって家にいてもストレスがかかることで、非行に走り、不登校になることもあります。
文部科学省の調査では、不登校の要因の一つとして「親の期待がプレッシャーになる」「親が厳しくて自由がない」「家庭に居場所がない」といった声が挙がっています。
また、親子関係において「親の期待が高すぎる」「干渉しすぎる」「逆に無関心で放任する」といったケースも、不登校につながることがあります。
さらに、親子の心理的な依存関係が強すぎる場合、子どもが「親から離れるのが怖い」「親がいないと不安」と感じ、登校できなくなるケースもあります。
【原因3】心身の不調が原因の場合
見落とされてしまいがちですが、心身の不調が原因で不登校になることもあります。 心身の不調例 ・病気 ・発達障害 ・体質(低気圧の日に不調が起こる、など) うつ病や起立性調節障害などの病気になっていると、朝ベッドから起き上がれず、めまいや動悸などの症状が出ます。 一見すると怠けてみえるので、周囲から誤解されやすく、余計に不登校を助長させてしまうこともあります。
中学生の不登校サインとは?
中学生が突然不登校になることはほとんどなく、事前に何らかのサインが現れることが多いとされています。
【身体的なサイン】
- 頭痛、腹痛、倦怠感、発熱、食欲不振
- 不眠・過眠(睡眠リズムの乱れ)
- 朝になると体調が悪くなる(登校時間に合わせて症状が出る)
【精神的なサイン】
- イライラしやすくなる、怒りっぽくなる
- 無気力、興味関心の喪失(好きだったことに興味を示さない)
- 憂うつ感が続く、ネガティブな発言が増える
【行動のサイン】
- 登校しぶり(遅刻・早退・欠席が増える)
- 保健室登校や別室登校が増える
- 学校の話題を避ける・拒否する
- スマホやゲームに依存する
- 外出を避け、部屋にこもることが増える
文部科学省の調査では、不登校の子どもたちは「学校に行かなければならないとは思っているが、どうしても体が動かない」と感じるケースが多いことが報告されています。
こうしたサインが見られた場合、「なぜ学校に行かないのか?」と問い詰めるのではなく、まずは子どもの気持ちに寄り添い、話を聞くことが大切です。
中学生に多い精神疾患
中学生は思春期の大きな変化を迎える時期です。
この時期に、不登校と関連する精神疾患が発症するケースが増えています。
文部科学省の最新調査によると、不登校の背景には「無気力・不安」や「体調不良」が大きく関係しており、精神的な問題が影響していることが示唆されています。
ここでは、不登校と関連の深い中学生に多い精神疾患について解説します。
【精神疾患1】うつ病
まず紹介する精神疾患はうつ病です。
もっともポピュラーであるが故に軽視されがちですが、最悪の場合自死に至りうる恐ろしい病気です。 それまで熱中していた趣味も楽しめなくなったり、人とのコミュニケーションが極端にできなくなったりします。
また近年、うつ病の原因はストレスや疲労にくわえ、ウイルスが関係していることも判明しました。
こちらの記事では、うつにかかりやすい人の性格について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。 関連記事:真面目な人が多い?うつにかかりやすい人の性格を解説
【精神疾患2】適応障害
次に紹介する精神疾患は適応障害です。
適応障害の症状はうつ病と似ていますが、趣味をはじめとした本人の楽しめることをしている際は症状が出にくくなります。
原因となるストレスが漠然としているうつ病と違い、原因が明確な点も特徴です。 主に、勉強が辛い、人間関係に悩んでいる、特定の授業が苦痛、などが挙げられるでしょう。
適応障害は原因に近づいたときにのみ顕著に症状が発現するため、理解されにくい精神疾患といえるでしょう。
【精神疾患3】統合失調症
次に紹介するのは統合失調症です。
症状は意欲の低下や妄想が挙げられ、酷くなると幻覚・幻聴にまで発展します。
そうなってしまうと治療の困難さも跳ね上がるため、早期発見が必要でしょう。
そのためにも、認知機能の低下や意欲の低下など、心理的な違和感を覚えた時点で専門医へ受診することが大切です。
関連記事:統合失調症の症状には種類がある!違いやタイプ別の特徴
【精神疾患4】起立性調節障害
起立性調節障害は、自律神経のバランスが崩れることで起こる病気です。
中学生の約1割が発症していると言われ、特に朝起きられない・体調が悪いなどの症状が特徴です。
この病気は、「サボり」や「怠け」と誤解されやすいため、本人も周囲も気づかないことが多いです。
学校に行けない日が増えたら、「体調が悪いのに無理している可能性がある」と考え、医療機関を受診しましょう。
中学生の精神疾患の治療法
中学生に多い精神疾患がわかったところで、ここからはそれらに有効な治療法を解説していきます。
主には以下の2パターンが存在します。
- 精神療法
- 薬物療法
それぞれ見ていきましょう。
【パターン1】精神療法
主にカウンセリングを経て、適切な心理療法を施します。 対話や訓練、簡単なテストなどを通しながら、認知機能の回復や、ときには生活指導を主軸に寛解(精神疾患の症状が抑えられている状態)を目指していきます。
【パターン2】薬物療法
薬物療法では、精神疾患や症状に合わせた薬物を使用します。
基本的に、治療薬としてではなく症状を抑える役割の薬という位置づけのものが多数です。
不登校の解決の一歩として、安心できる病院を受診しよう
いかがでしたでしょうか。
この記事を読んでいただくことで、中学生が不登校になる原因がご理解いただけたと思います。
不登校は学校でのトラブルが原因のケースもありですが、家庭の問題や心身の不調が原因になっていることもあります。
気になる症状があるときは、メンタルクリニックの受診を検討してみてください。
赤羽すずらんメンタルクリニックは駅から約1分で着く女性医師の心療内科です。
赤羽で心療内科をお探しの方はコチラをご覧ください。
監修者