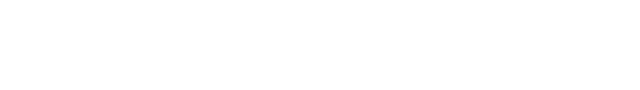心療内科で診断書をもらったときの退職手続きはどうする?注意点も
この記事では、心療内科で診断書をもらった方に向けた、退職手続きについて解説します。
うつなどが理由で仕事を続けることが困難となった場合、どのような流れで職場に伝え、退職したらよいのでしょうか。
通常の退職とは異なる手続きがあるのかどうかも気になるところです。
退職にともなう一連の手続きを順に分かりやすくご説明しているので、退職を検討している方はぜひご覧ください。
心療内科で診断書をもらった際の退職手続き
退職願の提出など手続きの流れを解説していきましょう。
退職届の提出
まずは退職の意志を会社側へ伝えます。
一般的に上司へ退職届を提出しますが、うつになった理由が上司にあるなど不都合が生じる場合は、人事担当者などに同席してもらうとよいでしょう。
心療内科で診断書をもらっている場合でも、自己都合の場合は退職届には一身上の都合、または体調不良と記載すれば大丈夫です。
職場のトラブルが原因でうつになった場合などは会社都合となりますが、その場合は意見の相違やトラブルを防ぐために就労支援機関に相談しましょう。
社会保険の手続きをする
退職時には健康保険や年金などの社会保険の手続きも行います。
雇用保険の加入期間が条件を満たしていれば、職場から離職票を交付してもらうことで退職後に失業給付の受給が可能です。
すぐに求職活動ができない場合は、失業給付の受給期間延長の申請をするか、雇用保険の傷病手当の申請を行います。
必要があれば労災の申請を
うつなどの病気が労働災害として認められる場合は、療養費の申請ができます。
しかし、うつが労災として認定されるには、精神障害発病前約6か月の間に業務による強い心理的負荷があったことが認められなければならないなど、ハードルが高いのが特徴です。
うつ病にはどんな初期症状があらわれる?心身のサインをチェック
休職期間を経て退職する際の手続きの注意点
うつ病などにより休職した場合、診断書などを提出して手続きすることで最長1年6か月間、健康保険の傷病手当金を受給できます。
条件を満たせば退職後も残りの期間分を受給することが可能です。
【傷病手当金受給条件】
- 退職日までに1年以上継続して健康保険に加入している
- 資格喪失時に傷病手当金を受給しているor受ける条件を満たしている
しかし、退職後に傷病手当金を受給する際には注意すべきポイントがあります。
それは、傷病手当金を受給している期間は前項で紹介した雇用保険の失業給付を受けることができないという点です。
治療中などの理由で傷病手当金を受給している場合は、失業給付の受給期間延長の申請手続きを行いましょう。
復職・再就職をする際は「リワーク」を
リワークとは「return to work」の略語で、うつ病などの精神疾患が原因で仕事を休職、または退職している方が職場復帰や再就職をする際、専門機関で行うプログラムのことを指します。
うつ病の再発リスクの軽減、予防にも効果があります。
こちらの記事では、リワークの基礎知識や特徴について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
「リワーク」とは?用語解説とリワークを行う意味
退職手続きは計画的に行いましょう
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで、心療内科で診断書をもらったときの退職手続きについてご理解いただけたと思います。
退職手続きは心身の負担とならないよう、ゆとりを持って行いたいですね。
赤羽すずらんメンタルクリニックは駅から約1分で着く女性医師の心療内科です。
赤羽で心療内科をお探しの方はコチラをご覧ください。
監修者